多様な働き方case:4 Blue Buck Diner バーガー修吾
小さなきっかけからの大きな始まり
男鹿市で地域おこし協力隊の任期を終え、キッチンカー(フードトラック)Blue Buck Diner を開業した大橋修吾さん。
男鹿での暮らしや地域おこし協力隊任期中のお話しは移住者インタビューで掲載しています。

こちらでは、開業に至るまでのお話しをうかがいました。


地域おこし協力隊を退任したら起業しようともともと考えていたんですか?
その時はハンバーガー屋をやるとは思ってはいませんでしたが、何かしら自分ができることを男鹿でやろうと考えていました。
地域おこし協力隊3年目にコロナが日本でも蔓延し、協力隊でおこなっていたレンタサイクルを数か月完全に休業をすることになりました。
再開しても全く人はこず、5日間この仕事をやっていなければならないなら空いた時間や休みを利用して少しづつハンバーガー販売に向けて準備を始めました。
もともとフリーランスで仕事をうける為に、協力隊の任期中に個人事業主として開業はしていました。

どうしてハンバーガーだったんですか?
協力隊の仲間と家でご飯を作って食べようということになりました。
前からハンバーガーを作ってみたかったこともあり、作ったものをみんなに食べてもらいました。
それを協力隊の同期が動画にしてくれて、Facebookに投稿したところ、多くのいいねをもらい、「食べてみたい」とコメントもいただき、改めて知人を集め、試食会をおこないました。
当時は、化世沢食堂がシェアキッチンで運用していたので、場所を利用して20人ぐらいに提供しました。
今提供しているものに比べたら味は劣りますが、普段この辺りではハンバーガーを食べれるお店はなかったので、「こういうのここで食べることができたらいいね。」と言ってもらえました。
その時は冷凍のバンズを通販で買って使っていましたが、美味しくないなと思っていたので、自分でバンズを作ることにしました。

その後も、ハンバーガーの販売を週1回のペースで化世沢食堂やトモスカフェを間借りをし、販売を始めていたら、SNSの口コミで人が来てくれるようになり、需要を感じました。
こういったきっかけもあり、改めて食に対しての市場調査をおこないました。
男鹿に観光で来る人が食べる場所やものを見ていると定食が多く、刺身定食や石焼鍋、付け合わせはギバサだったりサザエなど海鮮物が多く、一回食べればしばらく食べなくてもいいのではと考えました。
うに丼やいくら丼などに比べて、それの為に男鹿に行くという感じではないですよね。
そうなると、1回来た人がリピートしてくれるまで、遠くなってしまうのではと思いました。

全然違うご飯の種類があれば、晴れた日にドライブがてら男鹿に来るきっかけになるのではと考えました。
特に若年層やインバウンドのお客さんとかはその傾向が強く感じました。
男鹿に来ているのにカツカレーを食べていたり、海鮮が苦手な人もいたり。
また、男鹿に来る交通手段は車、自転車、バイクのお客さんが多いのにテイクアウトで楽しめるグルメがほぼないなと思いました。
今は、駅前に少しづつできてきましたけど、調べていた時はハンバーガーやサンドイッチのお店は40km圏内にはなく、某有名チェーン店も秋田市の飯島まで行かないとないので、そうすると需要があるかなと。
―すごく調査されたんですね。
事業計画書を書いて説得させないといけないので、そうでもしないと融資は通らないですからね(笑)
Blue Buck Diner (ブルーバックダイナー)にした由来を教えてください。

Blue(ブルー)は車の色、
Buck(バック)はオスの鹿という意味で、オスの鹿や一部の動物のオスのことをbuckといいます。
オスの鹿=男鹿
Diner(ダイナー)というのはアメリカにあるもともと電車の使わなくなった客間を道路横において、パンケーキやハンバーガー、フライドチキンなどを提供しているお店をダイナーと言いますが、そういうお店がやりたいと思ったので、この名前にしました。

今後のビジョンを教えてください。
少し前は迷走していました。
ビジネスを大きくしていこうというよりかは、自分がほんとに好きなものを通して、その好きなものでつながったり、コミュニケーションをとったりすることに面白味を感じているので、ハンバーガーでぼろ儲けしようとかハンバーガー屋さんをフランチャイズ化しようという気はないですね。
けど現状本当は、もっといろんなメニューを作ったり、どこかのお店とコラボしてハンバーガーメニュー作ったり、そういったことをやりたいのに、売り上げをあげていかなければ、自分が生活していけないことに追われ、やりたいことができていなかった1年でした。
だからこそ自分が生きていける分の仕事は他の所で作るために、就職しました。
これからは、もう少しやりたいことにもっと近づけられるように両立しながらやっていきたいと思っています。
【写真提供:Blue Buck Diner】
関連インタビュー記事
男鹿関係人口01 初めて親元を離れ、初めて降り立った東北の地!

この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課 移住定住促進班
電話番号:0185-24-9122
ファックス:0185-23-2922
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
メールフォームによるお問い合わせ

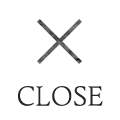



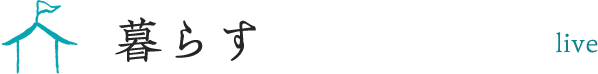
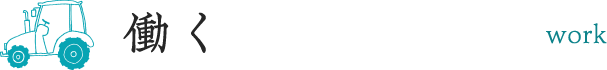
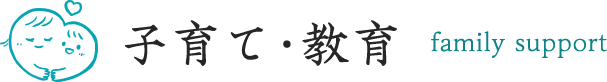
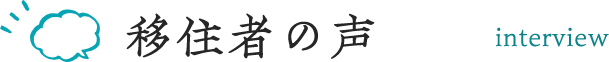
更新日:2022年12月02日